まずはこの写真を見てください。

はじめこの写真を見た時、男性の手にしているものがなんだかわかりませんでした。そしてよく見てそれが植物(穀物)の根だと知って非常に驚きました。密集した根が人の背丈まで延びている!
この男性ゲイブ・ブラウンの右側は通常の耕した土地に育った穀類の根です。男性の頭頂部あたりまでしか伸びていません。一方左側は耕さなかった土地で育った同じ穀類の根です。男性のひざ下まで伸びています。しかも密集度は右側と比べ物になりません。
耕さないで作物が作れるわけがない。雑草の生命力に比べたら、作物はとても弱くて負けてしまうじゃないか!
そんな意見がほとんどでしょう。耕す(cultivate)は文化(culture)にの語源になっている。人間が狩猟採取から農耕生活に移行することで文化が生まれたんだ、という考えなんでしょう。つまり今の文化的な生活は農耕によってもたらされたのだから、耕さないなんて人類の発展を否定するようなものじゃないかと思うのは普通の流れです。
しかし実際にブラウンが25年以上耕していない土地の土はまるでチョコレートケーキのように黒く、すっとスコップが入っていく。一方隣の耕した土地の表土は茶色く乾燥してコンクリートのように固い。
不耕起栽培は単に耕さないだけではない。それをブラウンは「土の健康5原則」とした。
1)土を耕さない(かき乱さない)
2)土を覆う(商品作物の合間にひまわりやささげなどの被覆作物を植える)
3)多様性を高める(数十種類の野菜や穀類や花を一緒に育てる)
4)土の中に「生きた根」を保つ(一年中何かしらの植物を育てる)
5)動物を組み込む(家畜を育てる)
不耕起栽培では農薬や化学肥料は使わないので、それに使う費用が節約できる。家畜もその土地の作物で育つので飼料もいらない。農機具に使う燃料も不要(ただし被覆作物をたおすための農機具ローラークリンパーは必要)。土の有機物は耕した土地に比べて3~4倍。害虫の発生も少なくなり水分の蒸発も減る。土の中の微生物や動物も豊かになる。そして収穫は2割もアップした。
不耕起農業は地球温暖化防止にも役立っているという。にわかには信じられない話だが、土壌には大気中の二酸化炭素の2倍以上が蓄えられているという。それを耕すことによって大気中に放出するというのだ。世界の温室効果ガス排出量の25%が農林業などの土地利用によってもたらされているという。有史以来農業活動で排出された炭素量は、産業革命後に化石燃料を燃焼させて排出された炭素量を上回るという。
全世界の土壌中にある炭素の量を毎年0.4%ずつ増やせば、人為的活動による大気中への温室効果ガスの排出を帳消しにできる、とフランス政府は言っている。その有力な手段が不耕起栽培ということになる。
日本は雑草が多くて不耕起栽培は手間がかかるという。しかし、不耕起栽培発祥の地は実は日本なのだ。ヴィネは1995年ころのテレビ番組で福岡正信氏の活動を知った。彼はその功績でアジアのノーベル賞といわれるマグサイサイ賞を受賞している。しかし彼の自然農法は哲学的、精神的な面が強調されていたため、一般の農家には広まらなかったようだ。しかしブラウンも福岡正信の影響を受けた一人である。

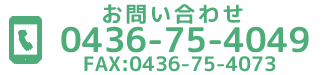

 (11 )
(11 ) 天童市は街の中心に公園があります。単なる公園ではなく、山になっています。これが結構高くて、トレイルっぽいところもあって、すごくいい練習コースになります。毎日ここで練習出来たら相当強くなりそうです。
天童市は街の中心に公園があります。単なる公園ではなく、山になっています。これが結構高くて、トレイルっぽいところもあって、すごくいい練習コースになります。毎日ここで練習出来たら相当強くなりそうです。 頂上から見た天童市の風景も素晴らしいです。ヴィネはここで2日間朝練をしました・
頂上から見た天童市の風景も素晴らしいです。ヴィネはここで2日間朝練をしました・ 突如目の前に現れたダム。留山川ダム。
突如目の前に現れたダム。留山川ダム。 道がありません。よく見る多何やら藪の中に看板が・・・。「・・・滝・・」と書いてあります。
道がありません。よく見る多何やら藪の中に看板が・・・。「・・・滝・・」と書いてあります。
 クラゲって見ていると、そのゆったりとした動きに癒されますよねえ。自分からはあまり強く主張せず、海流に流されて移動するのが移動の主な手段です。ふと立ち止まって、そんな生き方もありかなと思ったりするのですが、毒をもつものも少なくないから、こいつら何考えてるかわかりません。個人的には大きなクラゲよりは小さなクラゲが群れなしている方がきれいだと思います。
クラゲって見ていると、そのゆったりとした動きに癒されますよねえ。自分からはあまり強く主張せず、海流に流されて移動するのが移動の主な手段です。ふと立ち止まって、そんな生き方もありかなと思ったりするのですが、毒をもつものも少なくないから、こいつら何考えてるかわかりません。個人的には大きなクラゲよりは小さなクラゲが群れなしている方がきれいだと思います。
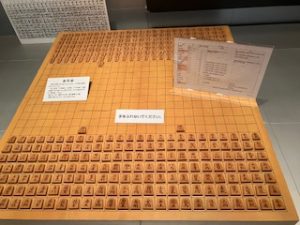 ヴィネが将棋を指したのは小学校のころだけですから、別段将棋に興味はありませんが、天童市に到着直後に一応資料館に行きました。
ヴィネが将棋を指したのは小学校のころだけですから、別段将棋に興味はありませんが、天童市に到着直後に一応資料館に行きました。 ホテルから約10キロの道のりをランしました。
ホテルから約10キロの道のりをランしました。

 ここに来て初めて知ったのですが、松尾芭蕉の有名な俳句はここで読まれたんですね。確かにこの山は巨大な石の塊って感じで、この岩の種類がデイサイト質凝灰岩というそうで、小さな穴があいています。ここにセミの声が染み入ると芭蕉が感じ取っても不思議ではないなとは思いました。因みに立石寺の階段は1000段以上あるそうです。
ここに来て初めて知ったのですが、松尾芭蕉の有名な俳句はここで読まれたんですね。確かにこの山は巨大な石の塊って感じで、この岩の種類がデイサイト質凝灰岩というそうで、小さな穴があいています。ここにセミの声が染み入ると芭蕉が感じ取っても不思議ではないなとは思いました。因みに立石寺の階段は1000段以上あるそうです。
 あれ?これだけ?
あれ?これだけ? むしろそのそばの岩だらけの地面に根を張ってまっすぐ天に向かって伸びる太い杉の木に感動しました。
むしろそのそばの岩だらけの地面に根を張ってまっすぐ天に向かって伸びる太い杉の木に感動しました。

 アンディほど耳が大きいと、この暑さでは耳が蒸れてうっとうしくなるのではないかという親心から、新たなファッションに挑みました。
アンディほど耳が大きいと、この暑さでは耳が蒸れてうっとうしくなるのではないかという親心から、新たなファッションに挑みました。 外に行きたがったので庭に放しました。おそらく何かめぼしい食い物が落ちていないかと、庭を歩き回ったと思います。しばらくすると勝手口にこの姿。吠えもせずただじっと待っているだけです。飼い主が悟ってくれるまで辛抱強く待つことができます。
外に行きたがったので庭に放しました。おそらく何かめぼしい食い物が落ちていないかと、庭を歩き回ったと思います。しばらくすると勝手口にこの姿。吠えもせずただじっと待っているだけです。飼い主が悟ってくれるまで辛抱強く待つことができます。

